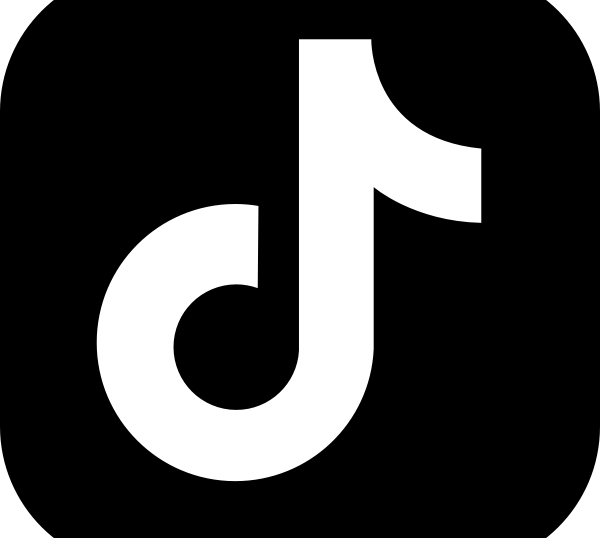⇒【東証プライム企業も多数利用!】最先端のSNSマーケティングツール「Tofu Analytics」、「InstantWin」とは?
近年SNSの中でも特に勢いのあるTikTokですが、アプリ内で入力したテキストを音声に変換して読み上げる「TikTokの音声読み上げ機能」が人気になっていることをご存じですか?
また、機能自体は知っていても、
「使い方がよくわからない…。」
「どんなメリットがあるの?」
といった疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回この記事では、
TikTokの音声読み上げ機能とは
TikTokの音声読み上げ機能の使い方
TikTokの音声読み上げ機能が使えない時の対処法
などを分かりやすく紹介・解説していきます。
ぜひこの記事を最後まで読んでTikTokの音声読み上げ機能を使いこなせるようになり、SNS活用のバリエーションを増やしていきましょう!

1.TikTokの音声読み上げ機能とは
TikTokの音声読み上げ機能は、動画に入力されているテキストを自動音声が読んでくれる機能です。使い方は簡単で、誰でもスムーズにボイス付きの動画を投稿できます。
1-1.現在利用できる音声の種類
TikTokの音声読み上げ機能には、2022年12月29日現在、例えば以下のような音声バリエーションが用意されています。
- ヒカキン
- 丸山礼
- 修一朗
- まちこりーた
- マツダ家の日常
- モジャオ
- モリスケ
- Sakura
- Miho
- Keiko
- Naoki
上記11種類が確認されています。音声のバリエーションは少しずつ増えてきて今に至っており、今後の追加にも期待がかかります。
ただし、そのペースは決して早くはないでしょう。
文章には無数のパターンがあります。それに対応できるほどの器用さを持った音声読み上げ機能を作るのはたいへんです。要は「Siriをいくつも作る」ような作業であり、時間もお金もかかります。
「もっと多くの音声が欲しい」と思うかもしれませんが、バリエーションが増えるまでは気長に待ちましょう。
2.TikTokの音声読み上げ機能のメリット
続いては音声読み上げ機能を利用するメリットについてご紹介します。
2-1.代わりに話してもらえるため便利
TikTokの音声読み上げ機能のメリットは、代わりに機械が話してくれること。自分自身で収録したり音のバランスを調整したりする必要がなくなります。
また顔出しどころか声出しさえも避けたいユーザーもいるでしょう。その場合は音声読み上げ機能を使うことで、プライバシーを守りつつ、伝えたい情報も伝えられます。
音声がなければ、面白さが確保できないジャンルもあるでしょう。例えば踊りや歌ではなく、何かをアピールしたり解説したりする趣旨の動画では、音声読み上げ機能が役立ちます。
ちなみに話し方は、やや機械的な部分があるものの基本的には上手です。「これが音声読み上げ機能によるものだ」と言われなければ、気がつかない場合もあります。
実際に@riiinodesuという美容系ティックトッカーによる動画を見てみましょう。
自然な喋り方ですが、本人の声でもナレーターでもなく、読み上げ機能の音声です。さすがに細かいニュアンスを伝えるなら人間のほうが優れていますが、それ以外に劣る部分は見当たりません。
2-2.補足説明や演出にも役立つ
TikTokの音声読み上げ機能は、いわゆる補足説明の場面でも活用されています。要するに大事な部分は自身で踊ったり話したりして、一部だけ音声に伝えてもらうやり方です。
例えば踊ってみた動画のあとに、フォローを促したり、プロフィールへ案内したりするようなアナウンスで活用できます。
演出で活用される一面も。やや特徴的なイントネーションと、いわゆる「ゆっくり解説」に近い脱力感や棒読み感は、時として人間よりも興味深く聞こえます。
自身の動画のクオリティを高めたいとき、音声読み上げが突破口になるかもしれません。
3.TikTokの音声読み上げ機能のやり方
続いてはTikTokの音声読み上げ機能の使い方を解説していきます。
3-1.投稿する動画を選ぶ
まず、TikTokの動画投稿画面に行き、右下のアップロードから投稿する動画を選択します。
3-2.読み上げたい文章を入力する
投稿する動画を選択したら、右上にあるテキストをタップし、自分が読み上げたい文章を入力します。
3-3.音声読み上げマークをタップする
次に、左にある音声読み上げマークを選択します。
3-4.声の種類を選択する
最後に、表示されている声の一覧から適用したい声を選択します。右上の完了をタップすることで音声読み上げ機能を利用することができます。
4.TikTokの音声読み上げ機能が使えない時の対処法
実は音声読み上げ機能はトラブルの報告が多く、正しく使いこなせていないケースもよくあるんです。
そこでここでは、読み上げ機能が使えない・正常に読み上げてくれない時などに活用できる、主な対処法を3つご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
それでは一つずつ詳しくチェックしていきましょう。
4-1.ログインせずに使用している
まず1つ目は、「ログインせずに使用している」ケース。
TikTokの音声読み上げ機能はログインをすることで使える機能であるため、ログインせずにアプリを使用するとテキストを入力した際に音声読み上げのマークが表示されません。
そのため音声読み上げ機能を使いたい場合は、まずログインしているかどうか確認するようにしましょう。
4-2.アプリのバージョンが最新でない
続いて2つ目は、「アプリのバージョンが最新でない」ケース。
TikTokに限った話ではありませんが、アプリが最新のバージョンでないと機能が正しく動作しないことがあり、TikTokの音声読み上げ機能も例外ではありません。
そのため、ログインをしているのに読み上げボタンが表示されない場合などは、アプリのバージョンが最新かどうか確認してみるとよいでしょう。
4-3.読み上げに対応していない文字を入力している
最後に3つ目は、「読み上げに対応していない文字を入力している」ケース。
TikTokの音声読み上げ機能は記号や特殊文字など、一部のテキストに対応していないため読み上げが失敗することがあります。
ただし、音声の種類によっても対応している文字が違うため、一つの音声で読み上げができない場合でも違う音声で試すと読み上げが上手くいくことも。
なお、TikTokアプリ外で作成してコピペした文章も読み上げ機能が動作しないため、アプリ外で文章を作らないことも注意点です。
5.TikTokの音声読み上げ機能を活用した事例
では、「企業は実際にどうやって活用しているんだろう?」と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの章では、企業がTikTokの音声読み上げ機能を活用した事例を3つピックアップしてご紹介していくので、利用時のイメージを明確にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
それでは詳しく見ていきましょう。
5-1.ドミノ・ピザ
アカウント名:@dominos_jp
フォロワー数:約36.3万人(2023年4月現在)
まず最初にご紹介するTikTokアカウントは、「ドミノ・ピザ」です。
宅配ピザ大手のドミノ・ピザは、定期的におこなわれるお得なキャンペーンやスマホによる注文をいち早く取り入れるなど、顧客に寄り添ったサービスが人気で幅広い年代から支持されているピザチェーン。
TikTokアカウントでは、実際にピザを作る様子やキャンペーン情報、ピザの豆知識などをメインに発信しています。
上記の投稿ではピザを2枚重ねで食べる様子を撮影し、「この食べ方したことある人いる?」と読み上げ機能を使って共感を呼びかけています。
音声を使うことでユーザーが話しかけられている気分になってコメントが増えやすくなると考えられ、通常100件前後のコメントが多いですが、上記の投稿には380件以上のコメントがついています。
また、動画が極端に短くシンプルであることも視聴者の反応を促す要因となっており、音声読み上げ機能の特徴である「情報の密度が高まる」ことがよく分かる事例といえるでしょう。
5-2.スシロー
アカウント名:@akindosushiroco
フォロワー数:約8.6万人(2023年4月現在)
続いてご紹介するTikTokアカウントは、「スシロー」です。
スシローはネタの美味しさや価格の安さなどが人気の回転寿司チェーン店で、仕入れ力や店内調理のひと手間が強みとなって長年の支持を得ています。
TikTokアカウントでは、ランキング動画やスシローでできる裏技、ネタ動画などをメインに発信しています。
上記の投稿では、スシローの隠れた人気商品であるえび天うどんを実質50円引きで食べられる裏技を読み上げ機能を使って紹介しています。
紹介されている手順としては、別々の2商品を組み合わせることで実質えび天うどんを作れるというもので、文字だけでは手順の説明が長くなったり難しくなるところを、可愛らしい音声を使って分かりやすく解説することでユーザーに伝わりやすい内容となっています。
また、実際に注文をしているシーンと合わせて紹介されているので、動画を見た視聴者が再現するために店舗に足を運びたくなるような動画づくりもポイントです。
5-3.GU
アカウント名:@gu_official
フォロワー数:約24.5万人(2023年4月現在)
最後にご紹介するTikTokアカウントでは、「GU」です。
GUは、低価格ながらトレンドを押さえたファッションアイテムを展開することで、若者から高い人気を得ているファッションブランド。
TikTokアカウントでは、トレンドの解説やシーンに合わせたコーディネート、注目アイテムの紹介などをメインに発信しています。
上記の投稿では、季節に合ったお花見コーデに使えるカーディガンを紹介しています。
読み上げ機能を使っているのは動画の冒頭部分のみですが、これから紹介される内容を簡潔に伝えることでユーザーの興味を惹き、動画の本編であるコーディネート紹介につなげています。
アパレル企業であればオンライン接客にように使うこともできるので、業種にあった使い方のバリエーションが多いことも読み上げ機能ならではの特徴といえるでしょう。
⇒【東証プライム企業も多数利用!】最先端のSNSマーケティングツール「Tofu Analytics」、「InstantWin」とは?